後遺障害等級認定とは?基本の決め方と例外への対応
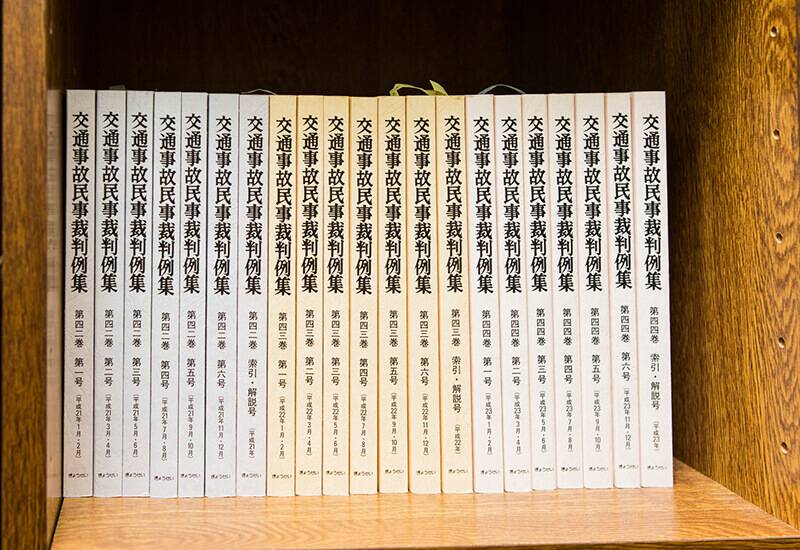
監修:弁護士 石田 大輔
所属:愛知県弁護士会
2020.12.26
Contents
後遺障害等級認定の基本
後遺症と後遺障害の違い
交通事故にあい、ケガを負うと入院や通院で完治を目指します。そこで一定期間治療・リハビリを行っても事故前の状態にならない後遺症が残ってしまった場合、医師はこれ以上医学的な処置では改善されないと判断し、症状固定と診断します。
症状固定後に残った神経症状や身体機能の問題は「後遺症」と呼ばれます。その後遺症のうち、「交通事故に起因していること」が医学的に証明され、労働能力の低下(またはは喪失)で日常の労働に耐えられないと認められると「後遺障害」と定義されます。
簡単にいえば、しびれなどの後遺症があっても、労働能力に影響がないものは後遺障害とは認められないということです。
具体的な例を挙げると、交通事故で脳に損傷を受け、記憶力が低下したり、手足に麻痺が残ったりした場合、これらは後遺症です。しかし、記憶力の低下が軽度で仕事に支障がない場合は後遺障害とは認められません。一方、手足の麻痺が重度で歩行や作業が困難な場合は、労働能力が大きく損なわれているため、後遺障害と判断されます。
症状固定日の決め方
症状固定日とは、交通事故による怪我の症状が将来ほとんど変わらない状態になった日です。法律で具体的な日数は定められておらず、治療の経過や本人の症状に基づいて医師が判断します。
判断基準には、1.治療効果の停滞、2.症状の軽度化、3.社会復帰の見込み があります。
1.治療効果の停滞とは、一定期間治療を続けても症状に変化がみられない状態を指します。例えば、半年間リハビリを行っても麻痺の程度に改善がみられない場合などです。
2.症状の軽度化とは、症状が残っているものの、日常生活に大きな支障がない程度まで回復した状態を指します。例えば、事故直後は歩行が困難だったが、杖があれば歩けるようになった場合などです。
3.社会復帰の見込みとは、現在の症状で職場復帰や家事・育児などの社会生活が可能と判断される状態を指します。例えば、事務職であれば片麻痺があっても、パソコン操作などの業務が可能な場合などです。
医師は、これらの判断基準を総合的に考慮して症状固定日を決定します。ただし、患者の主観的な症状も重要なので、患者側は症状の変化を医師に伝えるとともに、セカンドオピニオンの活用を検討することが推奨されます。
後遺障害等級とは?
後遺障害等級とは、交通事故等によって生じた後遺症を1級から14級まで14段階に分類し、後遺障害の程度を客観的に評価するための基準です。
1級が最も重症であり、等級が上がるにつれて軽症となります。後遺障害等級は、事故の被害者に対する賠償金の公平性を確保するために設けられています。
等級ごとに定められた後遺障害慰謝料は、後遺症の重症度に基づいて算定されます。 代表的な後遺障害等級は以下の通りです。
《1級 両眼の失明、両上肢の機能喪失など》
具体例:脳損傷により植物状態になった場合、頸髄損傷で四肢マヒになった場合など
《7級 一眼の失明、両耳の聴力障害など》
具体例:事故で片目の視力を完全に失った場合、両耳の聴力が70デシベル以上失われた場合など
《14級 むち打ち症など》
具体例:頚椎捻挫で運動制限や局所の疼痛が残る場合、腰椎捻挫で腰部の運動制限や疼痛が残る場合など
このように、後遺障害等級は身体の部位や障害の程度に応じて細かく分類されています。等級が上がるほど賠償金額も高くなるため、適正な等級認定が重要になります。
後遺障害等級認定の詳細
後遺障害は14段階の等級に区分される
保険金支払いの視点は、後遺障害の症状の程度や部位に応じ、「労働者災害補償保険法施行規則」に於いて14段階の後遺障害等級に区分された等級によって補償金額が決定されます。
この14等級の内容を具体的に見ていくと、どの部位が、どのようになった場合に、何級に認定されるかが細かく決められ、その数は35系列、140種類にも及びます。認定審査のときは、保険会社から提出された書類と照らし合わせ、該当する等級を決定していきます。
例えば、「脊柱の著しい変形で神経症状を伴うもの」は7級、「脊柱の著しい変形」は9級に認定されます。また、「胸腹部臓器の機能に著しい障害を残すもの」は5級、「胸腹部臓器の機能に障害を残すもの」は7級になります。
このように、後遺障害等級表では身体の部位ごとに、障害の程度に応じて等級が細かく定められています。
後遺障害等級認定の難しさ
ただし、交通事故にあった場合、35系列140種類の中にない後遺障害が発生したり、複合的に障害が残ったりすることもあります。このような場合、「併合」「相当」「加重」といった方法で処理されます。
1.複数の系統に及ぶ後遺障害をひとつにまとめる「併合」
一回の事故で複数箇所に後遺障害が残る場合があります。複数の系統の違う後遺障害は、それぞれの後遺障害の等級で見られますが、最終的にひとつの後遺障害にまとめて処理を行います。この処理が併合です。
具体的には以下のような処理が行われます。
・第5等級以上に該当する後遺障害が二以上ある場合、最も重い方の等級を3つ上げる。
・第8等級以上に該当する後遺障害が二以上ある場合、最も重い方の等級を2つ上げる。
・第13等級以上に該当する後遺障害が二以上ある場合、最も重い方の等級を1つ上げる。
・第14等級に該当する後遺障害が二以上ある場合でも14等級のままである。
例えば、事故で片目が失明し(7級)、片足の機能も全廃した(5級)場合、より重い5級の等級を3つ上げ、2級と認定されます。
2.後遺障害等級表に該当しない後遺障害を認定する「相当」
自賠法施行令別表第一及び第二に定められていない後遺障害が残った場合にはどうでしょうか。後遺障害等級表(自賠法施行令別表第一及び第二)のどれにも該当しない後遺障害についても、その部位や程度に応じて各等級に「相当」するものとして等級を定めることとなっています。
例えば、ある後遺障害がどの後遺障害の系列にも属さない場合や、属する系列はあるものの、該当する後遺障害が規定されていない場合が考えられます。
具体的には、事故で脳に損傷を受け、高次脳機能障害が残った場合などです。高次脳機能障害は後遺障害等級表に明記されていませんが、その症状の程度に応じて、各等級に相当するものとして認定されます。例えば、記憶障害や注意障害が重度で日常生活に著しい支障がある場合は、2級や3級に相当すると判断されることがあります。
3.すでに障害があった人の障害が重くなった場合の「加重」
事故以前に後遺障害のあった人が交通事故にあい、既存の後遺障害部分をさらに悪化させ、後遺障害の程度が重くなることを「加重障害」といいます。
この場合、交通事故後(障害の度合いが交通事故により重くなった状態)の後遺障害の保険金額から、交通事故以前の後遺障害(交通事故以前のケガで後遺障害が認定されているもの)の保険金額を控除した額を限度として保険金が支払われます。なお、すでにあった後遺障害は交通事故が原因のものかどうかは関係ありません。
例えば、事故前から片足に障害があり8級と認定されていた人が、事故で同じ足を負傷し、障害が悪化して5級になった場合、8級の保険金額を5級の保険金額から差し引いた額が支払われます。
後遺障害等級認定に強い弁護士に相談することの重要性
以上のように後遺障害等級を申請し、その等級に対応して慰謝料が決まっていきますが、申請する後遺障害は千差万別で、簡単に判断できるものではありません。判断基準は細かく決まっているようで、実際にどこに当てはめればよいのかの判断は曖昧さが残るのです。
特に、複数の後遺障害が組み合わさっている場合や、後遺障害等級表に当てはまらない後遺障害の場合は、等級認定が難しくなります。また、保険会社側は、できるだけ等級を低くしたいと考えるため、被害者側の主張をそのまま認めてくれるとは限りません。
そのため、医学的な知識と法律の専門性を兼ね備えた弁護士に相談することが大切です。弁護士は、後遺障害の状態を適切に把握し、それを裏付ける医療記録や検査結果を整理した上で、保険会社との交渉にあたります。
また、示談交渉だけでなく、裁判での主張・立証も視野に入れて後遺障害等級認定に取り組むため、適正な等級を勝ち取る可能性が高くなります。
ですから専門家たる医師や弁護士と相談しながら後遺障害等級の申請を話し合っていくことが望ましいというわけです。後遺障害等級認定を有利に進めるためには、交通事故に強い弁護士にご相談ください。
まとめ:後遺障害等級認定の基本と例外
後遺障害等級認定は、交通事故被害者の補償額を決める重要なプロセスであり、14段階で評価されます。一般的には症状固定後の後遺障害の種類や程度で等級が決まりますが、例外的な対応も必要となる場合があります。
後遺障害等級認定は、被害者の生活や人生に大きな影響を与えます。適正な等級認定により十分な補償が得られる一方、そうでない場合は生活の質の低下や経済的困窮につながる可能性があります。
医師と弁護士が連携し、被害者を全面的にサポートすることが重要です。医師は後遺障害の状態を正確に評価し、弁護士は被害者の権利を守り適正な補償を得るための支援を行います。
交通事故被害者は、まずは専門家に相談することが大切です。適切なサポートを受けることで、後遺障害等級認定の課題を乗り越え、公正な補償を得ることができます。
